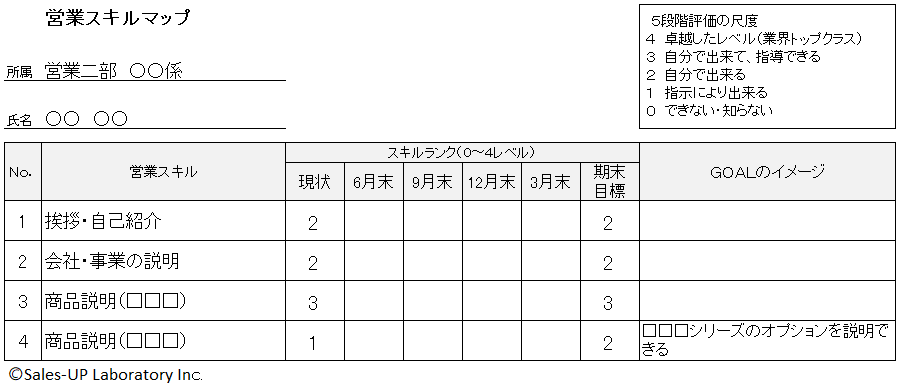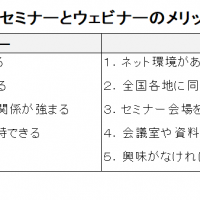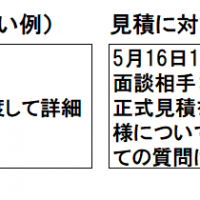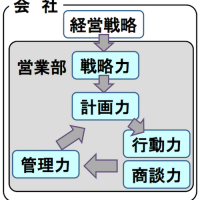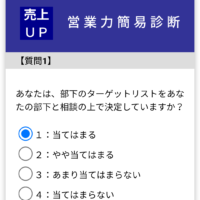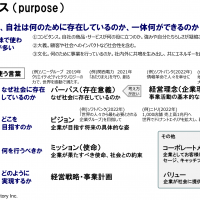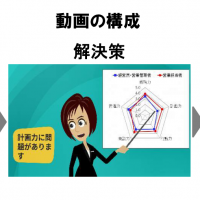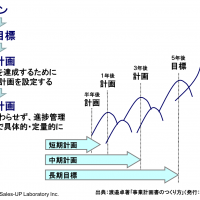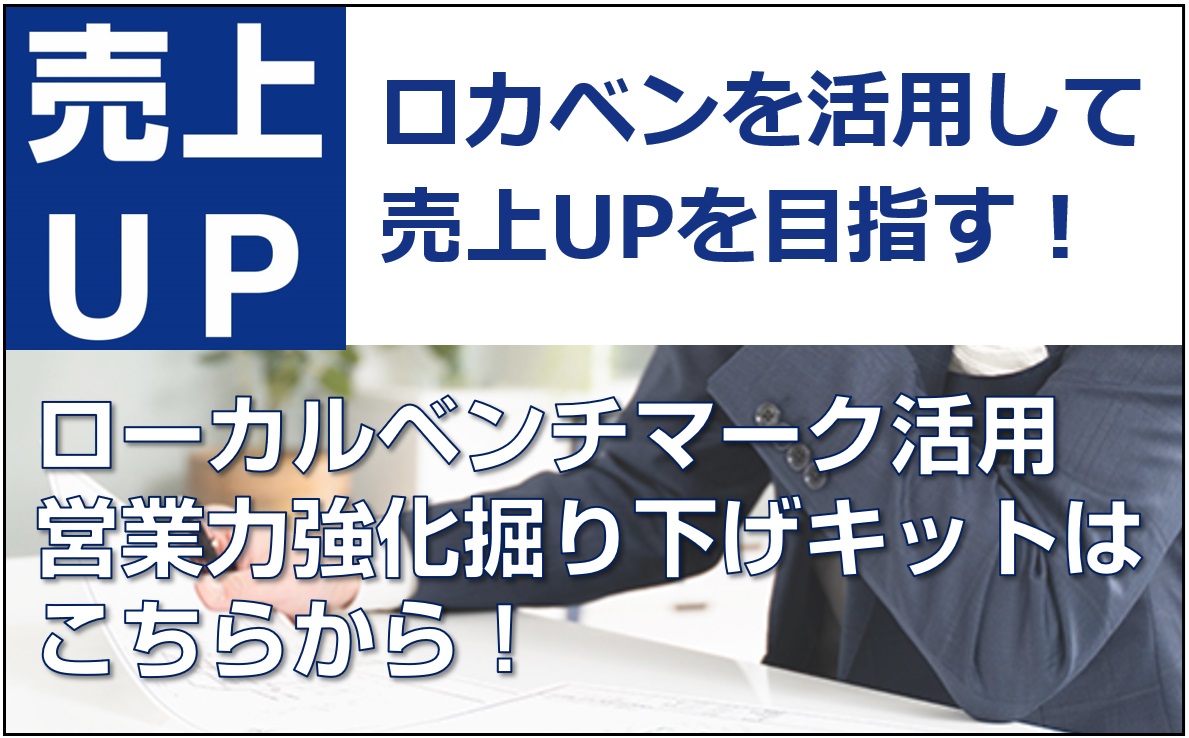属人営業を脱却!スキルマップで営業力を底上げする
なぜスキルマップが求められているのか
「ある人だけが実績を出して、他のメンバーが追いつかない」。
これはよく見られる現象です。経験や勘という属人的な要素に依存している限り、人による成績の差は避けられません。組織として営業力を底上げするためには、「何をできるか/できていないか」という、スキルに着目することが有効です。
スキルマップとは、自部署に必要な知識・スキルを選び、各人の現状をスコア化して、当人と上司が目標を決めて、スキルを一緒に育成していく仕組みです。今回の記事では、「スキルマップ導入で得られる効用」「スキルの構成」「スキルマップの運用方法」の3つを整理していきます。 このスキルマップは、営業以外の業務にも広く活用できますので、各業務にあてはめて活用してください。
2:6:2の法則は営業組織にも当てはまる
2:6:2の法則とは、どのような集団(組織、人間関係など)においても、上位2割が優秀、中間6割が普通、下位2割が不調に分かれるという経験則です。
これは営業組織にも当てはまります。そして、指導・育成することで変化するかどうかの観点から、次の通りまとめました。
上位2割:指導しなくても成果を出す
中間6割:指導することで変化しやすく、最も伸びしろがあり、組織成果を左右する層
下位2割:指導しても成果が出にくい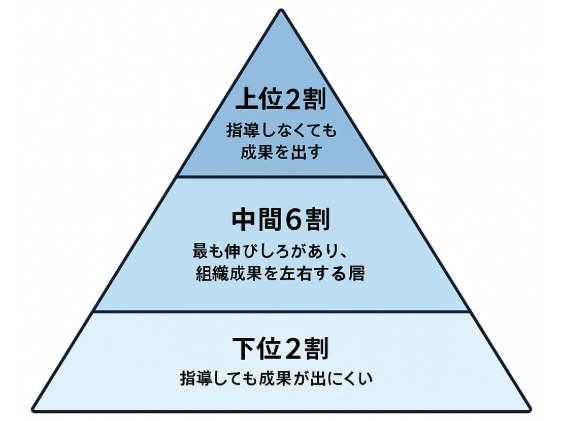
組織として成果を出す最短ルートは、指導・育成することによって変化しやすい「中間6割」を底上げすることです。6割もあるのですから、この層を少し上げるだけで、成績の改善が期待できます。中間6割を押し上げるには、属人的な指導ではなく、スキルマップによって「何をできるようにするか」を明確にする仕組みが不可欠です。
スキルマップ導入で得られる効用
ずばり、以下の4つが期待できます。
①可視化・言語化
各業務に必要な知識とスキルを明確にし、組織で共有することで、何を身につけるべきか可視化・言語化されます。さらに、上位2割のノウハウを営業スキルに分解することで、だれでも学べる形に落とし込めます。
②現状把握・育成
スキルの現状を当人と上司が共有し、目標設定と育成計画につなげられます。共通言語で把握できるため、的確な指導が可能になります。
③OJTの改善
「何をできるようにするか」を明確にすることで、OJTのバラつきをなくし、戦力化までの時間を短縮できます。
④営業プロセスの標準化
営業プロセスを標準化し、組織全体の業務効率を高められます。属人的なやり方がなくなり、営業プロセスがスムーズに回るようになります。
スキルの構成
スキルは大きく分けて、①製品・業界知識、②営業・関係構築スキル、③業務スキル、という3つのジャンルで構成されます。
① 製品・業界知識
自社の商材・仕様・特徴・価格・競合比較など
業界構造・トレンド・法規制・顧客課題の理解など
「何を売るか」を理解することが、全ての営業活動の基盤となります。
② 営業・関係構築スキル
ヒアリング・情報収集、提案・プレゼン、クロージングなど
顧客と信頼関係を築き、課題解決に導く「営業の核」となるスキルです。
③ 業務スキル
見積書作成、受発注処理、与信管理・代金回収、クレーム対応など
営業を安定運用するための実務スキル。ここが弱いと顧客満足が下がります。
スキルマップの運用方法
スキルマップは次のような5ステップで進めていきます。
Step1:スキル項目の定義
各業務に必要なスキルを明確にし、組織で共有する
Step2:当人と直属の上司による現状評価
当人と直属の上司がキャッチボールしながら、現状のスキルを5段階で評価する
Step3:目標の設定
期末の目標スキルとGOALのイメージを共有する
Step4:育成計画の策定
育成すべきスキルに対して、いつまでに、何を、どのように、を明確にする
Step4まで作成したスキルマップをご覧ください(下図)。
「挨拶・自己紹介」から始まるスキルが記入され、現状のスキルが0,1,2,3,4の数字で表されます。一番右側に期末の目標が記載されます。スペースの関係でお見せできませんが、下の方に育成計画があります。
Step5:定期的にレビューを行う
上図のスキルマップでいえば、6月末、9月末、12月、3月末と3か月ごとにレビューを行います。
遅れが生じていれば、当人と直属の上司とで対策を話し合いましょう。
上位2割だけに依存する組織では、成果は安定しません。スキルマップにより「全員が一定レベル以上の営業力」を発揮できるようになれば、組織の成果は飛躍的に伸びます。属人営業から、仕組みで強くなる営業組織へ。中小企業こそ、スキルマップ導入の効果は非常に大きいので、ぜひ実践してみましょう。